
投資にはさまざまな種類があり、特にFXや株式投資は知名度が高く、副業として取り組んでいる方も多いでしょう。
しかし、これらは値動きが激しく短期的な変動リスクも大きいため、「将来の資産形成を兼ねて、もっと安定的に運用したい」と考える方には必ずしも向かないケースがあります。
そこで注目したいのが投資信託です。
投資信託は、複数の投資家から集めた資金を専門の運用会社が株式や債券、不動産などに分散投資し、少額からでも手軽に、かつ安定的に運用できる金融商品です。
日々の値動きに一喜一憂する必要がなく、プロに運用を任せられるため、投資初心者や忙しい副業プレイヤーにも向いています。
この記事では、副業として投資信託を始めるための基本知識と具体的な手順をわかりやすく解説します。
「初めての投資だけど失敗は避けたい」「少額から安全に始めたい」という方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
投資信託とは

投資信託とは、複数の投資家から集めた資金をひとつの大きな資金プールにまとめ、ファンドマネージャー(資産運用の専門家)が株式・債券・不動産・その他の金融商品に分散投資・運用する仕組みを持つ金融商品です。
一般的には「ファンド」とも呼ばれます。
投資家は出資額に応じて運用成果(利益や配当)を受け取りますが、実際の運用判断はファンドマネージャーが行うため、どの投資信託を選ぶかが成績を左右する重要なポイントとなります。
株式投資のように自分で銘柄を選び、売買のタイミングを判断する必要がないため、金融知識が少ない方や投資初心者でも始めやすいのが魅力です。
また、証券会社やネット証券によっては、100円〜数千円程度の少額から購入可能な商品も多く、副業や長期の資産形成にも適しています。
- 運用は専門家に任せられるため、手間がかからない
- 複数の資産に分散投資できるのでリスク軽減効果がある
- 少額から始められるため、初心者や副業投資にも向いている
投資信託の仕組
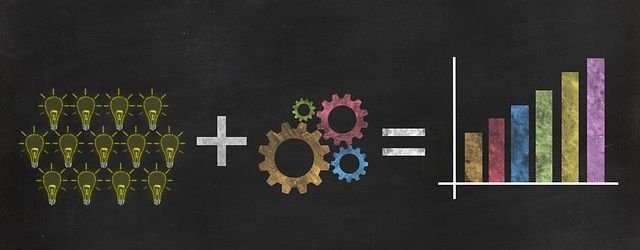
投資信託は、まず投資信託運用会社によって企画・設計されます。
こうして作られた投資信託(ファンド)は、証券会社や銀行といった金融機関を通じて投資家に販売されます。
証券会社や銀行は、すでに多くの顧客基盤を持っているため、投資家募集の窓口として非常に効果的で、大口の資金も集まりやすくなります。
投資家から集められた資金は、信託銀行に安全に保管されます。
実際の資産運用は運用会社が担当し、株式や債券、不動産などへの投資配分や売買のタイミングを決定します。
このとき、信託銀行はあくまで資産の保管と記録管理を担い、運用そのものには関与しません。
- 投資信託運用会社:ファンドの設計・運用方針の決定・売買の指示
- 証券会社・銀行:投資信託の販売窓口として投資家に商品を提供
- 信託銀行:投資家から集めた資金を安全に保管し、資産管理を行う
このように、資金の募集・運用・保管がそれぞれ別の機関によって分業されている点は、投資信託の大きな特徴です。
役割を明確に分けることで、透明性の確保とリスク分散が図られ、投資家は安心して資金を預けることができます。
投資信託のメリット・デメリット

投資信託を始める前に、メリットとデメリットの両面を理解しておくことは非常に重要です。
どの投資商品にもリスクとリターンが存在しますが、それを事前に把握しておくことで、自分に合った投資戦略を立てやすくなります。
投資信託のメリット
- 少額から始められる:証券会社やネット証券によっては、100円〜数千円というわずかな資金から投資可能。初心者や副業投資家でも参入しやすい。
- 運用をプロに任せられる:ファンドマネージャー(資産運用の専門家)が市場分析から投資判断までを代行するため、投資経験や専門知識がなくても始められる。
- 分散投資でリスク軽減:複数の銘柄や資産クラス(株式・債券・不動産など)に自動的に資金が振り分けられるため、一つの投資先が不調でも全体への影響を抑えられる。
- 幅広い投資先にアクセス可能:個人では投資が難しい新興国市場や特殊な資産(海外不動産、コモディティなど)にも間接的に投資できる。
投資信託のデメリット
- 元本保証がない:市場環境の変化によっては元本割れする可能性がある。安全性を重視する場合は運用先のリスクレベルを事前に確認する必要がある。
- 自分の裁量で運用できない:運用はすべてファンドマネージャーに委託するため、投資タイミングや銘柄選定を自分で決めることはできない。
- 短期的な利益を得にくい:基本的に中長期運用を前提としており、即効性のある利益は期待しづらい。短期売買には向かない。
このように、投資信託は少額・分散・プロ運用という大きな魅力がある一方で、元本割れのリスクや運用の自由度が低いという制約もあります。
副業として取り入れる際は、自分の投資目的や許容できるリスクに合わせて商品を選ぶことが重要です。
投資信託を始める4つの手順

投資信託は、手軽に始められるとはいえ適切な手順を踏まなければ、思わぬリスクや想定外の損失につながる可能性があります。
特に、副業として長期的な資産形成を目指す場合は、事前の準備と計画が成果を大きく左右します。
ここでは、投資信託を安全かつ効果的に始めるための4つのステップをご紹介します。
- 1. 資産の運用方針を決める(リスク許容度・投資期間・目標金額を明確化)
- 2. 購入する投資信託の選定(運用成績・手数料・投資対象を比較)
- 3. 購入窓口の口座開設(証券会社や銀行などで専用口座を準備)
- 4. 投資信託を購入する(少額から始めて運用をスタート)
これらの手順を順番に実行することで、投資信託の運用がスムーズに始められ、リスクを抑えながら安定的な資産形成が可能になります。
それでは、それぞれのステップを詳しく解説していきましょう。
1、資産の運用方針を決める
投資信託を始める前に、まずは資産運用の方針を明確にすることが最も重要です。
これは「どのくらいの期間で」「いくらの資産を目指すのか」という具体的な目標を設定する工程で、後のすべての判断基準となります。
目標が明確になれば、リスク許容度や運用スタイル(安定重視か成長重視か)も自然と決まり、商品選びや投資配分の判断がスムーズになります。
逆に、方針が曖昧なまま運用を始めると、相場変動に振り回されやすく、計画的な資産形成が難しくなります。
- 投資期間(短期・中期・長期のいずれか)
- 最終的な目標金額(例:5年で300万円、10年で1000万円など)
- 毎月投資できる金額と元手資金の総額
- 許容できる損失額やリスクレベル
この方針が定まれば、自分に合った投資信託のタイプ(株式型・債券型・バランス型など)や地域・分野を選びやすくなります。
「早い段階で運用方針を決める」ことは、投資信託で着実に資産を増やすための第一歩です。
2、購入する投資信託の選定
投資信託は証券会社や銀行ごとに取り扱う種類や本数が異なり、同じ投資信託であっても販売窓口によって手数料やサービス内容が異なることがあります。
そのため、購入先や商品選びを誤ると、思わぬコスト負担や運用効率の低下につながる可能性があります。
投資信託を選定する際には、以下のポイントをしっかり比較・検討しましょう。
- 手数料:購入時手数料(販売手数料)、保有中の信託報酬(運用管理費用)、売却時の信託財産留保額など、総合的なコストを比較。
- 投資対象:株式、債券、不動産(REIT)、コモディティなど、運用対象の資産クラスや投資地域を確認。
- 純資産額の推移:純資産が安定して増加しているファンドは、投資家からの信頼や資金流入が多く、運用の安定性が期待できる。
- 運用方針:成長重視型(株式比率高め)か、安全重視型(債券比率高め)かなど、自分のリスク許容度に合っているかを確認。
加えて、過去の運用実績や運用チームの評価、運用期間の長さなども参考になります。
「安い手数料 × 自分に合った運用方針 × 安定した純資産の推移」が揃った投資信託を選ぶことで、長期的に安心して資産運用を続けやすくなります。
3、購入窓口の口座開設
投資信託を始めるためには、まず証券会社や銀行で専用口座を開設する必要があります。
口座開設には大きく分けて「店舗型」と「ネット型」の2つのスタイルがあり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
- 担当者が直接説明やサポートをしてくれるため、初心者でも安心
- 対面で質問できるので、不安や疑問をその場で解消しやすい
- 一方で、人件費などのコストが上乗せされるため、ネット型より手数料が高め
- 口座開設や取引がすべてオンラインで完結し、手数料が安い
- 商品ラインナップが豊富で、比較・検索も容易
- 対面サポートはないが、投資信託に関する情報はネット上で十分入手可能
特に現在は、ネット上で信頼できる投資情報や比較ツールが豊富に揃っているため、必ずしも対面サポートが必要というわけではありません。
費用を抑えて効率的に取引したい副業投資家には、総合的に見てネット型口座の開設がおすすめです。
まずは自分の投資経験やサポートの必要性、コスト面を総合的に判断し、最適な口座タイプを選びましょう。
4、投資信託を購入する
口座開設が完了したら、まずは購入資金を口座に入金します。
入金が反映されたら、いよいよ投資信託の購入手続きに進みます。
投資信託の購入方法にはいくつか種類があり、自分の投資スタイルや目的に合わせて選択することが重要です。
- 金額買付:購入する金額を指定して買付する方法。初心者や少額投資から始めたい方におすすめ。
- 口数買付:購入する口数(投資信託の単位)を指定して買付する方法。購入数量を明確に管理したい場合に向いている。
- 積立買付:毎月一定額を自動的に買付する方法。ドルコスト平均法を活用でき、価格変動リスクを平準化できる。
積立買付は特に、副業で忙しく日々の価格チェックが難しい方や、長期的な資産形成を目指す方に適しています。
一方で、短期的な売買やスポット購入を行いたい場合は、金額買付や口数買付を活用すると柔軟な運用が可能です。
いずれの場合も、購入方法の特徴・手数料・約定日などを事前に確認し、自分の運用方針に合った買付方法を選びましょう。
投資信託運用の注意点

これまで解説してきた通り、投資信託は運用のプロ(ファンドマネージャー)に全てを委託できるため、金融知識が乏しい初心者でも比較的始めやすい投資商品です。
また、証券会社やネット銀行を通じてオンラインで口座開設が可能なため、手続きの手軽さも魅力のひとつです。
しかし、「プロに任せられる=放置しても良い」というわけではありません。
運用を成功させるためには、ファンド選び・運用方針・コスト管理・リスク分散といった基本的なポイントを押さえる必要があります。
ここからは、投資信託の運用を始める際に必ず意識しておきたい3つの注意点について解説します。
分散投資でリスクを軽減させる
たとえ運用のプロであるファンドマネージャーに資産を任せたとしても、必ずしも利益が保証されるわけではありません。
市場環境や経済情勢によっては、利益が出ないどころか元本割れを起こすリスクも常に存在します。
このリスクを軽減するために有効なのが分散投資です。
1つの投資信託や特定の資産クラスに資金を集中させず、複数の投資信託や異なる資産へ資金を分けることで、一部が不調でも全体の損失を抑えられる可能性が高まります。
- 資産クラスの分散:株式・債券・REIT(不動産)・コモディティなどに分けて投資する
- 地域の分散:日本国内、先進国、新興国など複数の地域に投資する
- 運用スタイルの分散:成長重視型(アクティブファンド)と安定重視型(インデックスファンド)を組み合わせる
特に副業として資産形成を目指す場合、長期的な安定性が重要になります。
分散投資は短期的な大きな利益こそ狙いにくいものの、資産を守りながら着実に増やすための基本戦略として欠かせません。
分配方法を十分に確認する
投資信託にはいくつかの分配方法があり、その中でも近年人気を集めているのが「毎月分配型投資信託」です。
このタイプは、毎月決まったタイミングで分配金を受け取れるため、定期的な収入が欲しい方に魅力的に映ります。
しかし、注意しなければならないのは、毎月分配=必ず利益を受け取れるわけではないという点です。
運用成績が悪い場合、分配金の中に元本が含まれる(または全額元本である)ケースも珍しくありません。
つまり、見かけ上は「分配金」という形で現金を受け取っていても、実際には自分が投資したお金を取り崩しているだけという可能性があるのです。
さらに、そこに販売手数料や信託報酬といったコストが加わると、元本割れが加速するリスクもあります。
- 分配金の原資が「利益」か「元本」かを確認する
- 分配頻度(毎月・年数回・満期時のみ)を理解する
- 分配金を受け取らず再投資する「再投資型」の選択肢も検討する
分配方法の魅力だけに惑わされず、ファンドの運用方針・過去の実績・コスト構造をしっかりと確認して選ぶことが、長期的な資産形成では何より大切です。
高額手数料による損失を避ける
投資信託には、運用そのものとは別にさまざまな手数料が発生します。
代表的なものとして、以下の3種類があります。
- 購入時手数料(販売手数料):投資信託を購入する際に支払うコスト
- 信託報酬(運用管理費用):保有期間中、運用会社に支払う継続的な費用
- 信託財産留保額:投資信託を解約(売却)するときに差し引かれる場合がある費用
同じ種類の投資信託でも、販売窓口や運用会社によって手数料率が大きく異なることがあります。
投資信託は基本的に長期運用で利益を積み上げていく商品ですが、高額な手数料はその利益を大きく削る要因になります。
例えば、信託報酬が年1.5%の商品と0.3%の商品を比較した場合、長期的には手数料差だけで数十万円〜数百万円の差が生まれる可能性があります。
そのため、購入前には必ず総コストを確認することが重要です。
最近では、購入時手数料が無料(ノーロード型)の投資信託や、低コストのインデックスファンドも増えています。
これらを活用すれば、手数料を抑えつつ効率的な資産運用が可能です。
長期で安定的に資産を増やすためには、「手数料はできるだけ安く」という意識を持ち、複数の商品や販売先を比較してから購入を決めましょう。
まとめ
投資信託は、株式やFXなどの投資方法と比べても始めやすく、安定性の高い金融商品のひとつです。
プロに運用を任せられるため、投資経験が少ない方や副業として資産運用を始めたい方にも適しています。
しかし、元本や利益が保証される商品ではないという点は忘れてはいけません。
市場環境の変化やファンドの運用方針によっては元本割れの可能性もあり、運用の成果は常に変動します。
そのため、最低限の金融知識を身につけたうえで、分散投資・コスト管理・運用方針の見極めといった基本を徹底することが重要です。
また、自分のリスク許容度や投資目的に合わせて、長期的に続けられる商品を選びましょう。
副業として投資信託を活用すれば、本業の収入に加えて中長期的な資産形成が可能になります。
まずは少額から始めて経験を積み、無理のない範囲で運用額を増やしながら、安定した資産運用の仕組みを作っていきましょう。














